はじめに
「うちの子、最近元気がなくて学校に行けない日が増えてきた…」「怠けているわけじゃないと思うけど、どう接していいかわからない」
そんなお悩みを抱えるご家庭は少なくありません。近年、子どもの不登校の背景に「うつ状態」や「うつ病」が関係しているケースが増えています。
この記事では、心理学的な視点から「不登校とうつの関係」と「家族ができるサポート方法」について、わかりやすく解説します。
1. 不登校の背景にある“こころの不調”
不登校は、単なる“怠け”や“甘え”ではありません。多くの場合、子ども自身も「学校に行きたい」「行かなきゃ」と思っているのです。
それでも行けない理由のひとつに、こころの不調=うつ状態が隠れていることがあります。
うつ状態のサイン(子どもの場合)
子どもや思春期のうつは、大人とは違った形で現れることがあります。例えば:
- 朝になると「頭が痛い」「お腹が痛い」と言う
- 食欲や睡眠の変化(寝すぎる・眠れない/食べすぎる・食べない)
- 元気がなくなり、会話が減る
- 好きだったことに興味を示さなくなる
- イライラしたり、急に怒ったりする
- 「どうせ自分なんて…」という言葉が増える
これらはすべて、こころのSOSかもしれません。
2. 不登校とうつの関係とは?
心理的ストレスが引き金に
不登校の背景には、さまざまなストレス要因があります。たとえば:
- いじめや友人関係のトラブル
- 勉強のプレッシャー
- 親や先生との関係
- 感覚過敏や発達特性(HSPやASD傾向など)
これらのストレスが長期化すると、自信を失い、自己肯定感が低下します。そして、「学校に行かない自分はダメなんだ」と自分を責めるようになり、うつ状態に陥ることがあります。
“仮面うつ”に注意
子どものうつ状態は、しばしば「身体症状」や「行動の変化」として現れます。これを心理学では「仮面うつ」と呼びます。
つまり、うつの「本当の気持ち」が、頭痛・腹痛・反抗的な態度などに“仮面”として現れるのです。
3. 家族にできる5つのサポート
子どもが不登校になったとき、家族の対応はとても大きな影響を与えます。心理学的に効果的とされる対応を5つご紹介します。
① 無理に登校させようとしない
「明日こそ行きなさい!」と責めたくなる気持ちはわかりますが、今の子どもにとって学校は“戦場”のような場所かもしれません。
まずは休ませること=“心を守ること”が最優先です。
② 気持ちに共感し、受け止める
「学校が怖い」「行きたくない」という気持ちを否定せず、
「そう思うのは自然なことだよ」「つらいんだね」と共感的に受け止めることが、子どもの安心感につながります。
③ 小さな変化を見逃さず、肯定する
たとえば「今日は起きれたね」「好きなことができたね」など、どんなに小さな一歩も見逃さず褒めてあげることが、自己肯定感を育てます。
④ “話さなくても一緒にいる”という安心感を
無理に会話を引き出そうとせず、ただ一緒にいる時間を大切にしましょう。沈黙も「ここにいていい」という安心感になります。
⑤ 専門家の力を借りる
うつ状態が疑われる場合は、スクールカウンセラーや児童精神科医などの専門家に相談することが重要です。
家族だけで抱え込まず、外部のサポートを活用しましょう。
4. 子どもは「回復する力」を持っている
不登校もうつも、時間と適切なサポートがあれば、必ず回復の方向に向かいます。
一番大切なのは、子ども自身のペースを尊重し、「あなたはそのままで大丈夫だよ」と伝え続けること。
家族の温かいまなざしは、子どもにとって最大の安心材料です。
おわりに
不登校は、「学校に行けないこと」ではなく、「今の環境が子どもに合っていない」というサインです。
そして、うつ状態は、そのサインの中でも見逃されがちですがとても重要なポイントです。
子どもが「自分のペースで回復していけるように」、家族ができることはたくさんあります。焦らず、寄り添いながら、一緒に歩んでいきましょう。
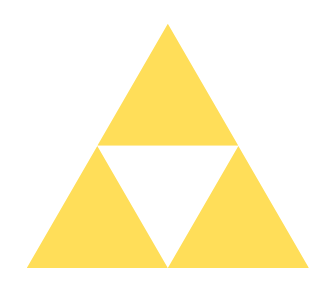


コメントを残す